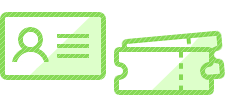龍馬ハネムーンウォークin霧島「隼人・天降川コース」
1866年土佐の坂本龍馬と妻お龍が日本で最初の新婚旅行で訪れ、雄大な自然や豊富な湯量を持つ温泉で激動の幕末で活躍したその身体を癒しました。まさにその温泉と神社を訪ねる天降川沿いの散策です。
全画面で見る
-
その他
鹿児島神宮-
 ヒコホホデミノミコト(山幸彦)とその御妃の茄玉姫を主神とし、仲哀・応神天皇・神功里后とを、合わせまつる。別名、大隅正八幡、国分八幡、大隅一ノ宮という。
明治以前は、正八幡宮あるいは鹿児島神社といった。社伝では、神武天里創建と伝え、平安時代の書物「延喜式」(927年成立)には、「大隅国桑原郡一坐大鹿児島神社」とある。これらに依っても、起源は相当古いものと思われる。現在の社殿は宝暦6年(1756年)に作りかえられたもの。
本殿拝殿の左手庭に宝暦6年の社殿造り替えを刻した石灯籠がある。神宮裏山の稲荷。
ヒコホホデミノミコト(山幸彦)とその御妃の茄玉姫を主神とし、仲哀・応神天皇・神功里后とを、合わせまつる。別名、大隅正八幡、国分八幡、大隅一ノ宮という。
明治以前は、正八幡宮あるいは鹿児島神社といった。社伝では、神武天里創建と伝え、平安時代の書物「延喜式」(927年成立)には、「大隅国桑原郡一坐大鹿児島神社」とある。これらに依っても、起源は相当古いものと思われる。現在の社殿は宝暦6年(1756年)に作りかえられたもの。
本殿拝殿の左手庭に宝暦6年の社殿造り替えを刻した石灯籠がある。神宮裏山の稲荷。
-
その他
石体神社-
 鹿児島神宮の元の宮跡といわれる。現在はお産の神様として信仰されている。お産の前にお参りして石を一ついただいて帰り、産後、母子共に再び参り、その時にお返しに、石二つ持参する風習がある。
神社右横に「高千穂宮趾」の石碑あり。
鹿児島神宮の元の宮跡といわれる。現在はお産の神様として信仰されている。お産の前にお参りして石を一ついただいて帰り、産後、母子共に再び参り、その時にお返しに、石二つ持参する風習がある。
神社右横に「高千穂宮趾」の石碑あり。
-
その他
蛭児神社-
 イザナミ・イザナギの二神の間にできた蛭児を、この楠(くす)の舟に入れて流したのが漂着した場所がこの神社といわれる。蛭児の乗った舟は、やがて根づき、どんどん成長して大きな森となった。これが今の奈気木(なげき)の杜であるという
イザナミ・イザナギの二神の間にできた蛭児を、この楠(くす)の舟に入れて流したのが漂着した場所がこの神社といわれる。蛭児の乗った舟は、やがて根づき、どんどん成長して大きな森となった。これが今の奈気木(なげき)の杜であるという
-
その他
西郷さんと隼人-
 戊辰戦争(1868年、明治元年)を終えて鹿児島に帰った西郷さんは息つく暇も無く、壮士数人と猟犬数頭を従えて、この隼人を訪れています。曰当山温泉にのんびりひたり、川で釣りに山でイノシシやウサギを追って遊んだと文献に記されています。
西郷さんは春夏秋冬と十数回にわたり訪れています。当時は旅館などはなく、農家のおもて座敷を借りて滞在しました。その農家、龍宝伝右ヱ門宅が現在、再現されています。
西郷さんが幾度となくこの地を訪れたのは曰当山温泉の泉質の良さもさることながら雄大な自然が西郷さんの心を引きつけたのです。
戊辰戦争(1868年、明治元年)を終えて鹿児島に帰った西郷さんは息つく暇も無く、壮士数人と猟犬数頭を従えて、この隼人を訪れています。曰当山温泉にのんびりひたり、川で釣りに山でイノシシやウサギを追って遊んだと文献に記されています。
西郷さんは春夏秋冬と十数回にわたり訪れています。当時は旅館などはなく、農家のおもて座敷を借りて滞在しました。その農家、龍宝伝右ヱ門宅が現在、再現されています。
西郷さんが幾度となくこの地を訪れたのは曰当山温泉の泉質の良さもさることながら雄大な自然が西郷さんの心を引きつけたのです。
-
その他
日当山侏儒どん-
 薩摩藩第18代藩主島津家久公に仕え日当山の地頭をつとめた徳田大兵衛という実在の人物。侏儒どんは背の高さがわすか3尺(約90cm)でしたが、頭の回転の早さは抜群で、殿様がどんな難問を出しても、スラスラと答えを返したといわれます。現在でも侏儒どんの頓知小話が数多く残っています。
薩摩藩第18代藩主島津家久公に仕え日当山の地頭をつとめた徳田大兵衛という実在の人物。侏儒どんは背の高さがわすか3尺(約90cm)でしたが、頭の回転の早さは抜群で、殿様がどんな難問を出しても、スラスラと答えを返したといわれます。現在でも侏儒どんの頓知小話が数多く残っています。
-
その他
菅原神社磨崖仏-
 磨崖仏は、自然の岩や崖面をけずり、仏像や梵字(ぼんじ)等を彫ったもの。
二体、四体、十三体といった風にセットで彫られている。右手神社参道横には、一体のみ十一面観音が彫られ、「天神御本地」の刻字も見える。年代は、天正〜慶長年代。神社との関係も注目される。
磨崖仏は、自然の岩や崖面をけずり、仏像や梵字(ぼんじ)等を彫ったもの。
二体、四体、十三体といった風にセットで彫られている。右手神社参道横には、一体のみ十一面観音が彫られ、「天神御本地」の刻字も見える。年代は、天正〜慶長年代。神社との関係も注目される。
-
その他
姫城湯本大権現碑-
 僧明源、鎌倉時代の永仁元年(1293年)の銘があることから、碑の建てられたのは鎌倉時代の後半期で、明源というお坊さんがお湯の出たことを記念して、湯源に石をご神体として湯の神様を祭ったものです。姫城地区の温泉の起源を知る上で重要な石碑です
僧明源、鎌倉時代の永仁元年(1293年)の銘があることから、碑の建てられたのは鎌倉時代の後半期で、明源というお坊さんがお湯の出たことを記念して、湯源に石をご神体として湯の神様を祭ったものです。姫城地区の温泉の起源を知る上で重要な石碑です
-
18km 330分
その他
鹿児島神宮-
 ヒコホホデミノミコト(山幸彦)とその御妃の茄玉姫を主神とし、仲哀・応神天皇・神功里后とを、合わせまつる。別名、大隅正八幡、国分八幡、大隅一ノ宮という。
明治以前は、正八幡宮あるいは鹿児島神社といった。社伝では、神武天里創建と伝え、平安時代の書物「延喜式」(927年成立)には、「大隅国桑原郡一坐大鹿児島神社」とある。これらに依っても、起源は相当古いものと思われる。現在の社殿は宝暦6年(1756年)に作りかえられたもの。
本殿拝殿の左手庭に宝暦6年の社殿造り替えを刻した石灯籠がある。神宮裏山の稲荷。
ヒコホホデミノミコト(山幸彦)とその御妃の茄玉姫を主神とし、仲哀・応神天皇・神功里后とを、合わせまつる。別名、大隅正八幡、国分八幡、大隅一ノ宮という。
明治以前は、正八幡宮あるいは鹿児島神社といった。社伝では、神武天里創建と伝え、平安時代の書物「延喜式」(927年成立)には、「大隅国桑原郡一坐大鹿児島神社」とある。これらに依っても、起源は相当古いものと思われる。現在の社殿は宝暦6年(1756年)に作りかえられたもの。
本殿拝殿の左手庭に宝暦6年の社殿造り替えを刻した石灯籠がある。神宮裏山の稲荷。
-
- 紹介URL
-
- 距離
- 18km
-
- 所要時間
- 330 分
-
- 所在地
- 鹿児島県
-
- コース
カテゴリ
-
ウォーキング
-
- コースの
特徴
-
新日本歩く道紀行 1000の道、トレイル(ロングトレイル)
-
- 1000の道 テーマ
-
水辺の道
-
- 推奨時期
-
春・秋
-
- 問い合わせ先名称
-
霧島市 観光課 観光地づくりグループ 霧島市観光協会
-
- 問い合わせ先電話番号
-
0995-78-2115
-
- 問い合わせ先URL
-
- 投稿者
- 特定非営利活動法人新日本歩く道紀行推進機...